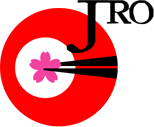
 >
> - JROについて >
- JRO REPORTS >
- 2015 >
- ミラノ万博特集 特別レポート
ミラノ万博特集 特別レポート
一覧へ
ミラノ万博への日本食レストラン出店は大成功
日本食文化を世界にアピール、外食「国際化元年」に弾み
「食」をテーマにしたイタリア・ミラノ万博が2015年10月末で、6か月間にわたる長期間のイベントに終止符を打つ。そこで、ミラノ万博で日本食文化を世界にアピールする重要な役割を演じた日本食レストラン7社によるコンソーシアム、それら企業群をバックアップした日本フードサービス協会(JF)、日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)の取り組み、その活動成果などについて、ミラノ万博の現場で見聞したことを踏まえ、特別レポートしよう。
(経済ジャーナリスト、メディアオフィス時代刺激人代表 牧野義司)
EUを軸に「日本食の市場づくり」が出来、世界への進出チャンスが増大
結論から先に申し上げよう。日本は、今回のミラノ万博を通じて、世界に対し日本の食文化をアピールし、それによって日本の食文化が間違いなく世界の市民権を得た、と言っていい。
とくにうれしいことは、その中核的役割をJFコンソーシアム企業が結束して果たしたことだ。日本の外食産業は、これまで個別には海外で市場展開してきたが、今回のように長期間にわたって、しかも「食」をテーマにしたミラノ万博という大舞台で、日本の食文化のアピールのために、みんなで結束力を強め、存在感を示した意味合いは大きい。
そればかりでない。JFコンソーシアム企業、JF、JROは、今回のミラノ万博での日本食評価の大きな高まりによって、これまでいろいろな意味で敷居の高かった欧州共同体(EU)を軸に、海外での日本食市場づくりができたことは大きな成果だ、とJF関係者は語っている。
中でもEU市場への展開の足掛かりができたのはプラスだ。というのも、EU市場の中核にあるフランス、イタリアといった、それぞれの食文化に強いプライドを持つ国々のシェフや調理人の間で、日本の食文化が「強み」にする旨(うま)味、とくに素材の味を引き出す旨味調味料に対する評価が着実に広がってきている。今回、その旨味調味料をふんだんに使った料理をミラノ万博で提示し、改めて高い評価を得たからだ。
日本パビリオンはピーク時に9時間待ち、日本フードコートも大人気


ただ、同時に、JFはじめ日本の外食産業は、今回のミラノ万博でさまざまなことを学んだのも事実だ。それらの課題を申し上げる前に、まずは、この6か月間の日本館の人気度、それに日本フードコートなどでの日本食レストランの奮闘ぶりを少しレポートしよう。
今回のミラノ万博特集1でも紹介したとおり、イタリアのイベント情報誌「ViviMilano」が6月末時点で行った人気パビリオンWeb投票結果で「一番きれい、すばらしい、見ごたえがある」パビリオンの第1位が日本、第2位は地元イタリアだった。
それを裏付けるように、私がミラノ万博会場の現場で見た日本館への入場は7月時点で約1時間待ちだった。ところが、8月のサマータイムに入って以降、5時間待ちがざらになり、終盤の10月に入ると、驚くことに行列の最後尾は何と9時間待ちとなった、という。
ミラノ万博の日本館は当初、入場者数に関しては140万人を見込んでいたが、いま申し上げたような日本館人気で、9月中旬には150万人を超え、さらに10月の閉幕少し前の10月下旬には何と200万人を突破した、という。
日本食レストランの1日あたり売上高は当初目標を大きく上回る3倍増に
これに伴い日本食レストラン1店&日本フードコートのレストラン4店(4店のうち2店が3か月ごとに交代し合計では7店が出店)の売上高も、当初予想を大きく上回る成果をあげた。
JF関係者によると、5店の売上目標に関しては当初、1日あたり2万3000ユーロ(円換算300万円)を見込んだ。ところが日本館への入場客がうなぎ上りに増えたのに比例して隣接する日本フードコートの売上高も急上昇、10月10日に1日あたり3倍の6万9600ユーロを記録したのを最高に、連日4万ユーロを大きく超す勢いとなった、という。
出店した企業は、すでにご存じのとおり、日本食レストランが和食の美濃吉、また日本フードコートはそばなど麺類のサガミチェーン、カレー&トンカツの壱番屋が万博開催期間中の6か月をフル操業、そしてすき焼、ステーキの柿安、人形町今半、ライスバーガー、テリヤキバーガーのモスフードサービス、寿司の京樽がそれぞれ2社ずつペアを組み、3か月交代で出店した。いずれも異文化の土地で、しかもあとで述べる安全文化に対する考え方が違う土地で、日本食文化をアピールすることに関しては言い知れない苦労があったのは事実だ。
調理人は、全ての企業が日本から社員を長期派遣した。万博期間中、まったく休館なしに毎日、営業時間の午前11時半から午後9時半まで、その前後の準備&後片付けを含めると、かなりのハードワークだった。でも、「食」という、言葉がなくても語り合える共通財を軸に、多くの人たちが日本食文化の担い手となったのは、素晴らしい、の一語に尽きる。

JFコンソーシアムが連携、オール・ジャパン型でスクラム組み難題に対応
今回のミラノ万博プロジェクトでの大きな成果は、冒頭に申し上げたとおり、JFコンソーシアムに参画した企業、それにバックアップのJFやJROが一体感をもって連携対応し、いわゆるオール・ジャパン型の行動をとったことだ。JF関係者によると、そのスクラムは、食材の日本からの調達、現地調達はじめお客様の感想などのフォローアップ、それをもとにした新たなメニューの導入などに関して、さまざまな形での連携効果を生んだ、という。
ただ、当初から万端整えてのスタートではなかった。日本政府のミラノ万博プロジェクトは当初、「一汁三菜」「ラーメン」や「甘味(スイーツ)」にスポットを当てたレストラン・コンセプトを打ち出していた。それに呼応するように、有名な和食レストラングループが出店を計画したが、それらグループが食材調達はじめ人材確保などをもとに事業化調査を行ったところ、EUの様々な規制への対応を含めて、予想外にハードルが高いことが判明し、最終的に断念せざるを得なかった。
そこで、農林水産省などから急きょ、外食産業を包括的に束ねるJFへの協力・参加要請が来た。JF関係者によると、JFとしては、日本の外食産業としての力をいかんなく発揮しやすいように調理・おもてなしの接客にとどまらず、食材調達・物流・厨房器具などのインフラとノウハウなどを注ぎ込んだ、文字どおり「オール・ジャパン」型のスクラムを組んだフードコート・スタイルで臨み、しかも幅広いメニューを展開すること、加えて本格的な京懐石料理店を併設するやり方で、日本の外食産業の「強み」部分を世界に向けてアピールするプロジェクトにしようということになった、という。
日本由来でない料理が独自に深化遂げ和食と融合し日本食文化に
こういった中で、JFやJROにとって、伝統のある和食が2013年12月にユネスコ(国連教育・科学・文化機関)の無形文化遺産として登録されたことはプラス材料だった。同時に、日本食文化が持つ「おいしい」「安全・安心」「品質管理が抜群」「おもてなしサービスがいい」といった「強み」をベースに、世界で日本食に人気が集まり、今や単なるブームから代表的な食文化という形で定着しつつあることも大きかった。
JF関係者は「和食がユネスコの世界無形文化遺産に登録されたことに関しては誇りに思っており、重要なことだとも思っています。ただ、日本の食文化は、その和食の枠にとらわれず、歴史的に、世界中から食材やメニューを取り入れ、うまく融合させて独自の進化・発展を遂げてきました。その代表的なメニューがてんぷら、すきやき、麺類、カレーライスです。また典型的な輸入メニューと言えるハンバーガーに関しても、『テリヤキバーガー』『ライスバーガー』といった形で事実上、日本食化を遂げてきました。これらのメニューがミラノ万博の会場で、寿司とともに認知されただけでなく『おいしい』といった形で受け入れられたことの意味は大きいと思います」と述べている。
このJF関係者の話を聞いていると、冒頭に申し上げたとおり、日本は、今回のミラノ万博を通じて、世界に対し日本の食文化をアピールし、それによって日本の食文化が間違いなく世界の市民権を得たとい言っていい。同時に、JFのミラノ万博への参加は「外食産業世界化元年」と位置付けたことがこの段階で花開いたばかりか、敷居が高いと言われたEUの全域での市場展開の足掛かりとなった、ともいえる。
今後は海外日本食レストランにコールドチェーンなど品質管理定着が課題
今や日本食レストランは海外で8万9000店に及び、それぞれの地域で根を張りつつある。しかしこれら海外の日本食レストランの経営実体は、日本食ブームにあやかって中国系、韓国系企業経営者が多いという現実も事実だ。そこでの問題は、日本食文化がこだわる味のよさ、安全安心の文化、品質管理のよさなどに関して、これら中国系などの企業経営者らがこの機会に、しっかりとした意識で「改革」に取り組んでくれるかどうかだ。JFやJROは、ミラノ万博で得た日本食評価が、これらの企業によって崩されないように、今後、フォローアップ作業が重要になる。
これは何も中国系などの企業だけの問題ではない。海外各地で事業展開している日本のさまざまな外食企業にもいえることで、JFやJROとしては、今回のミラノ万博をきっかけに、日本食文化をしっかりと構築するためのガバナンスづくり、さらには海外の日本食レストラン展開にあたって、日本の強み部分である冷凍・冷蔵のコールドチェーンシステムなど品質管理を軸にしたインフラづくりに向けての体制整備、安全や衛生管理を軸に調理技術を磨くことなどが必要になってくる。
この点に関して、JF関係者は「それらはすべてオール・ジャパンで対応していく課題で、今回のミラノ万博で日本外食企業が得た大きな教訓だと思います」と語っている。
EU安全衛生基準HACCP対応も課題、鰹節などはミラノ限定
ポスト・ミラノ万博を考えた場合、課題はまだある。これまで日本政府は、外国産農産物・食品から自国の農業、食品加工企業を守ることに重きを置いてきたため、EUなどの外国の輸出先市場における規制やさまざまな要件をクリアするための戦略対応、規制緩和に向けての交渉などに、残念ながら、重きを置いてこなかったことは事実だ。
具体的には欧米において食品加工・製造の安全基準となっているHACCPに関して、日本はその導入が遅れている。このため、日本の水産加工物を筆頭に、HACCPの基準を満たしきれていない農産物や食品に関しては、EUに対して、ほとんど輸出が出来ない。動植物検疫も同様で、肉類や園芸作物に関しては、輸出国がまず輸出先の国々に対して品目ごとに門戸を開けるための「リクエスト(要望)」書類を提出しなくてはならない。豚肉もしかりだ。これまで、そういった「リクエスト」を出していなかったため、EUに対しては輸出がされたことがないばかりか、それ以前の交渉も行われていなかった。
そういった中で、これまでEU基準を満たしていない「禁制品」とされ、輸入が認められなかった鰹節と生鮮(冷凍)豚肉について、日本政府は対イタリア政府との必死の交渉を行い、ミラノ万博特区だけでの使用限定ということで搬入が認められた。
日本産豚肉を使ったトンカツは大人気、しかし厳しい採算
とはいえ、JFやJROの関係者の話を総合すると、日本における豚肉の最も代表的なメニューとしてアピールしたトンカツは大好評を得たが、トンカツ用の生鮮(冷凍)豚肉を日本からミラノ万博の日本フードコートの調理現場に輸送するまでの行程1つとっても問題山積だった。

具体的には、日本から千葉県産の「いもぶた」を200キロ分、空輸しミラノまで運んだが、まずEUの「禁制品」扱いのため、厳重な監視のもとでの輸送が義務付けられ、しかも現地ミラノ空港到着後、関税や輸送料以外に、政府指定倉庫に運び込むこみが要求され、追加費用負担が求められた。そればかりでなかった。日本フードコートの冷凍庫のスペースでは大量保存が難しいため、ミラノ万博会場から遠方の政府指定倉庫に一時保存され、調理で必要な時に少量ずつ搬入され、その度にイタリア政府衛生当局担当者が立ち会いのもと開封するなど、大変な手間がかかった。
このため「日本フードコートではトンカツが人気で売れ行きがよくて売り上げ増になっても、実際にはきわめて高コストのため、採算ベースにはまったく乗らないつらさがありました」と関係者は語っている。今後、日本の外食企業がEU市場に本格的な進出を考える際、これらハードルをどうクリアするか、という問題が残っている。
JFコンソーシアムが得た教訓多い、今後は物流などロジスティック対策
この点に関連して、JFやJRO関係者によると、今回のミラノ万博で得た今後のEU市場への本格進出にあたっての教訓は、日本の外食企業がEUで日本の農林水産物を輸入するに際して、数多くの制限、規制があること、これらをクリアするための努力が必要であること、また、日本からEUへの物流システムなど、ロジスティックやインフラがまだまだ未整備で、その対応も急務であること、さらに日本の外食企業がEUで現地法人を設立して事業展開するにあたって会社設立手続きの法制面での対応、付加価値税など税制の研究といったビジネス立ち上げのノウハウも必要であることなどが判明した、という。これらの問題クリアも間違いなくポストミラノ万博対策として、重要だ。
JF関係者は「その点でも、オール・ジャパンでの取り組みがますます重要だと思います。とくに、民間企業サイドでは農業、食品産業、そして外食産業に加えて厨房機材の企業、物流企業などロジスティックにかかわる企業なども含めての、文字どおりオール・ジャパンでの全員参加でやる取り組みが必要です」と述べている。
JF「外食産業国際化元年」にリンクしアウトバウンド、インバウンド戦略に
JFは、2015年度事業計画で、「『アウトバウンド』の海外展開の推進と同時に、“おもてなし精神”“観光立国日本への貢献”など『インバウンド』需要の獲得を含めた包括的な取り組みを加速する。『食』がテーマであるミラノ万博に日本館レストラン部門の運営主体として参加し、関連産業とともに日本食、日本食文化の普及と国産食材の・食品の輸出促進に努める」ことを打ち出している。
JF関係者は「JFの創立40周年時に、私たちは『外食産業国際化(グローバル化)元年』の年にするのだ、とし、事業計画でもそれを5つの柱の1つに加えましたが、今回のミラノ万博は、JFが事業計画目標にしていた『日本外食国際化元年』を早くも実現させてくれた、と言っていいです。いろいろな課題が山積ですが、間違いなく今回のミラノ万博での日本食評価への高まりによって弾みがついたと言っていいです」と述べている。これらの話を聞く限り、ミラノ万博はJF、JROに大きな、新たな飛躍への一歩を促したと言えそうだ。







