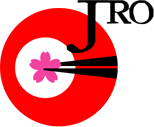
 >
> - JROについて >
- JRO REPORTS >
- 2016 >
- 日本外食企業のEU本格進出はビジネスチャンス
日本外食企業のEU本格進出はビジネスチャンス
一覧へ
カギはEUの輸入食品の安全規制緩和への対応、オランダの現場報告
昨年のイタリア・ミラノ万博での日本食文化に対する評価の高まり、とくに日本フードコートでの外国人客の日本食メニューへの反応のよさから手ごたえを感じた日本フードコート参加企業を含め日本の外食企業関係者の間でフランス、ドイツ、イタリア、オランダなどEU(欧州共同体)市場への本格進出を検討、という声が出たのは間違いない事実。
ミラノ万博の教訓、カツオブシなどはEU食品基準に抵触し搬入できず
ただ、ミラノ万博に参加した日本の外食企業にとっての大きな教訓は、カツオブシやトンカツ用の豚肉を日本から万博会場の日本フードコートに持ち込もうとした際、EUの食品規制(特に、ベンゾピレン等の発がん性物質含有量)の基準に抵触とする、としてEUへの物資の搬入にかなりの時間を要したことだ。
特に、日本産豚肉はこれまでイベント用すら輸出取り扱いの実績が全くなかったことから、当初は全く認められなかったが、日本政府がEU及びイタリア政府と粘り強く交渉した結果、最終的に「ミラノ万博会場内のみ例外的に使用(万博特例措置)」が何とか適用された。
日本フードコート・プロジェクトにかかわった日本食レストラン7社のコンソーシアム、それら企業群をバックアップした日本フードサービス協会(JF)、日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)にとっては、いまだに苦い思い出だ。しかし問題は、日本の外食企業が今後、EUに本格的に市場参入する場合、このEUの食品規制への粘り強い対応がカギとなる。
そこで、「オランダに学ぶ」最終回は、日本の外食企業がEUに本格進出する際のカギとなるEUのHACCP取得に加えて様々な食品基準への対応に関して、EUの中核国オランダの首都アムステルダムにあるホテルオークラの調理現場で、どういった対応をしているか、現場レポートをしてみよう。
現地ホテル総料理長「郷に入れば郷に従えで順守、あとは強み生かせ」
アムステルダム・ホテルオークラ前総料理長で、現在も幅広くビジネス展開されているJROアムステルダム支部長の大島晃さんに調理現場見学のアレンジをお願いし、現場ではアムステルダム・ホテルオークラの和食レストラン山里のシェフで、和食部門の総料理長の富川正則さんに当時、HACCPへの取り組みの現状や対応課題などをお聞きした。
まず結論から先に申し上げよう。富川さんによれば、和食が国連ユネスコの無形文化遺産に登録されたのをきっかけに、日本食文化の持つ味へのこだわり、味のよさなどに対する世界中の人たちの関心度が高まった。ミラノ万博で日本食人気が一気に開花した。その点で、日本の外食企業がグローバル世界、とくにEUにビジネスチャンスを求めて積極展開されることを望む。EU食品安全管理基準HACCPに関しては、当初、私たちも日本食の品質管理に自負を持っていたので、それを受け入れることに抵抗があったが、HACCPは、いざ現場で対応してみると、それなりに合理的なシステムで、納得できるものも多い。むしろ日本の外食企業は「郷に入れば郷に従え」でルールを順守し、逆に日本食の強み部分をしっかり生かし、その強みを武器にEU市場でチャレンジされたらいい、という。

和食レストラン山里 和食部門
総料理長 富川正則氏
調理用まな板はプラスチック板を義務付け、魚や肉などで色違いを使用

調理用まな板はプラスチック板を義務付け
そこで、さっそく現場のホテル調理場でのHACCP対応を具体的にレポートしよう。まず調理器材のまな板は日本料理の場合、寿司の握りはすべてヒノキのまな板を使うのが常識だが、HACCPにもとづいて魚をさばいたり、野菜のカットなどのまな板はすべてプラスチック製で、調理素材によって魚用、肉用、野菜用など、それぞれの用途ごとに異なるプラスチックを使う。そのまな板はプラスチックの色によって使い分けるのがルール。
富川さんによると、アンチバクテリア対応の高級な木製の、ヒノキのまな板などが和食現場ではあるが、EUではHACCPのルールに従わざるを得ない。魚をさばくプラスチックのまな板はすべらないように、まな板の下にスポンジを置いたりする、という。
また、調理に際しては、和食調理でポピュラーな布巾はいっさい使えない。まな板の上で魚の水分をとったり、またまな板の上の水分をとる場合、すべてキッチンペーパーかロールペーパーで対応する。
寿司など和食に必須のコメのシャリを入れる特別仕立ての桶も使えず、炊飯器をそのまま使う。寿司用のシャリの温度は人間の肌の、いわゆるヒトハダ温度の37、8度に保つ必要があるので、この保温の温度管理も必要。
富川さんの話では、ご飯は、HACCPの基準ルールに従って、当日に炊いたものは当日に使い切ることが必要で、残した場合、廃棄処分が義務付けられている。日本では、チャーハン(焼き飯)などで活用したりするが、オランダを含めてEUでは認められない。このため、お客の入り具合、注文具合をみて、ご飯を大きく残さないようにする維持管理判断が問われる。サバを使った押し寿司なども、常温で置いておくと、チェックに来るインスペクターから「放置しているのか」と問題指摘が入る、という。
日本から輸入の養殖真鯛、日本近海魚はすべてHACCP指定市場経由
和食に欠かせない魚に関しては、マグロはスペインやポルトガル沖合で獲れ、HACCP仕様でチェックされたものを市場で買って調理に使う。日本からは毎週1回、飛行機便で搬入する。真鯛、シマアジ、カンパチ、ハマチを仕入れるが、このうち九州で養殖した真鯛に関しては、HACCP基準を満たした指定の養殖場のものを使う。それ以外の魚は、HACCPの指定を得ている鹿児島、熊本の2つの卸売市場経由のものしか使えない、という。
また、野菜に関しては、和食調理に欠かせない本ワサビ、ミョウガ、ミツバ、シシトウガラシ、オオバ、ユズ、スダチなども週1回の飛行機便で搬入するが、タネのあるものは搬入禁止で、原産地証明がないと搬入許可がおりず、スダチなどに関しては、いつも苦労する、と富川さんは話している。
これら以外の現地オランダ産の野菜を適宜、調理に使うが、サイズがバラバラ、葉っぱが固くて調理しづらい、品質も安定しないなどの問題があり、その点でも日本産野菜は市場流通制度で鍛えられているせいか、品質やサイズなどではレベルが高い、という。

日本から空輸しているオオバ
有名店の衛生管理チェックは厳しく、インスペクター対応スタッフも配備
富川さんは「調理場の衛生管理面では、日本の調理現場の経験だと、水回りには細心の注意を払っている、という自負があるが、オランダではさらにチェックが厳しく、排水路はバクテリアの発生を防ぐため、すべてタイル張りを義務付けられる。ホテルオークラの山里などのレストランは有名店なので、とくにチェックが厳しく、監視人のインスペクターの見回りも頻度が比較的高い。このため、私たちもインスペクター対応のスタッフを置き、毎月1回のスタッフミーティングでは課題対応などのレポートの提出を現場スタッフに求めるほど」という。
ただ、富川さんは「HACCP対応をしっかりすれば、こわいものはない、と自負できる。あとは本来の強み部分の味や見栄え、サービスのよさなどで付加価値を上げて、勝負すればいい。ありがたいことにアムステルダム・ホテルオークラの和食の山里、鉄板焼きのさざんかのレストランはいずれも90%が地元オランダ人で、残りが日本人、外国人客と安定している。1人当たりの客単価もそれぞれ80ユーロ(円換算9440円)、150ユーロ(同1万7700円)と割高ながら、お客の満足度は高く、うまくいっている」と述べているのが印象的だった。
(経済ジャーナリスト 牧野義司)







