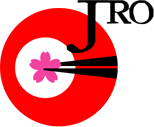
 >
> - JROについて >
- JRO REPORTS >
- 2015 >
- ヤンゴン国際シンポジウム レポート No.1
ヤンゴン国際シンポジウム レポート No.1
一覧へ
ミャンマーで2月に日本食の国際シンポジウム
アジアに進出する日本食レストランの「食の現地化」に討議集中
今や単なるブームから、世界的な食文化として定着した日本食文化をアジアにもっと広めていこう、という狙いから、特定非営利活動法人(NPO)日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)は2015年2月5日、ミャンマーのヤンゴンで、ミャンマーレストラン協会(MRA)との共催により国際シンポジウムを開催した。
ミャンマーの外食関係者や現地メディア関係者らが加わり総勢200人が参加する盛況ぶりだった。2時間に及ぶシンポジウムは、興味深い議論となり、シンポジウム終了後に開催したメニュー提案会でもミャンマーの人たちの日本食への関心が高く、日本食文化がミャンマーで着実に広がっていくことを印象付けた。
シンポジウムは、「世界で拡大する日本食およびフードサービス産業の成長戦略」をテーマに、ミャンマーレストラン協会の幹部を交えパネルディスカッション形式で行われた。
パネリストは、ミャンマーレストラン協会副会長のネイ・リン氏(セイン・ラン・ソービエー・ガーデン・レストラン社長)、JF副会長・国際交流委員会の粟田貴也委員長(株式会社トリドール代表取締役社長)、株式会社ハチバン執行役員海外運営部長清治洋氏、味の素株式会社執行役員外食デリカ事業部長の八馬史尚氏、それにコーディネーターとして日本食レストラン海外普及推進機構(JRO)の加藤一隆専務理事が加わった。



ニャン・リンMRA前会長が直前急逝、日本との民間交流橋渡し役に哀悼
加藤氏は冒頭、ミャンマーレストラン協会のニャン・リン会長がシンポジウム前の今年1月に急逝されたことに哀悼の意を表明した。そして日本フードサービス協会(JF)やJROが2011年のミャンマー軍政の民政移管による民主化以降、ミャンマーレストラン協会との食文化を通じた文化交流によって日本とミャンマーの関係強化に努めたが、故ニャン・リン会長は、その民間交流の橋渡し役になって大きな役割を果たしていただいた、と功績をたたえた。
その際、加藤氏は、JFやJROが窓口になって、2013年、2014年と2回にわたってミャンマーレストラン協会の関係者を日本に招いて、セントラルキッチン方式による外食現場の効率的な調理システム、品質管理技術などを研修してもらうと同時に、日本農業の現場見学など交流を深めたことを明らかにした。
そして、加藤氏は今回、ミャンマーレストラン協会の関係者から異口同音に「あの時の日本との食文化交流がいろいろな形でミャンマーの外食レストランのレベルアップにつながった。これからも日本のノウハウを学び取りたい。本当に感謝している」との言葉をいただき、改めて私たちの民間ベースでの交流の重要性を再認識した、と語った。
MRA副会長は「日本研修で学んだ品質管理などが役立った」と感謝表明
これを受けて、パネリスト参加したネイ・リン氏もパネルディスカッションの最初の部分で、「今、ミャンマー経済は着実に発展を遂げ、レストランビジネスもチェーン展開する店が増えるなど、大きな広がりを見せている。この急成長のきっかけをつくってくれたのは間違いなく日本だ。私たちミャンマー企業が2013年、14年の日本研修でチェーン店の経営システム、とくにチェーン展開した場合、同じ味をどうやって維持するか、さらには品質管理だけでなく衛生管理をどこまで徹底するかなどを学んだことは、今になって、いろいろな形で生きている」と述べた。
このあと、パネリストは、それぞれの企業のアジアでの取り組み、とくに日本の食文化が世界の新たな成長センターとなりつつあるアジアで着実に存在感を見せ始めていることをいくつか事例をあげながら、語った。
続いて、パネルディスカッションの焦点は、日本の食文化をアジアに定着させる場合、日本の企業が各国や地域でどのように現地化すればいいと考えているのか、という点に移った。端的には現地の食のニーズ、味の好みなど、それぞれの現地の志向にどこまで合わせるのか、あるいは日本食文化の持つ独自性にこだわるのかどうか、という点だった。
粟田氏がインドネシアでの現地パートナーの進言受入れ成功事例を披露
まず、粟田氏が、この点に関して、インドネシアでの経営体験を語った。粟田氏が経営する株式会社トリドールは、夫婦二人で小さな焼き鳥屋からスタート。「お客様に本物のおいしさを届けたい」という創業当時の思いを原点に,現在セルフうどん「丸亀製麺」を国内外に展開している。
粟田氏によると、インドネシアはミャンマーと同じく有望な成長市場と見て、日本のうどんを食べてもらいたいとマーケットリサーチし出店準備を進めた。外資規制の関係でインドネシアのパートナーとの合弁形態の出店模索となったが、いざ現実問題として、うどん味に対する現地の志向の違いで、パートナー選びにかなり苦労した、という。
ところが運よく現地の1社が名乗りを上げてくれ、「食の現地化」に対応しながら、試行錯誤の上に出店したら大成功だった。お客さんに食べてもらう単価は、現地の相場に比べて決して安くなかったが、努力のかいがあって何と1日1000人ものインドネシアの人たちが来店してくれ、大当たりだった。その後、インドネシアでは経営に弾みがつき、その店を軸に16店舗の出店数になっている、と粟田氏は述べた。
粟田氏はその際、成功のポイントが現地化、とくに味の面で現地のインドネシアの人たちの好む味にした点だ、と述べた。具体的には、丸亀製麺は日本での讃岐うどんに使っているトッピングのネギやショウガにこだわったが、「それでは売れない」という現地パートナーの進言を受け入れて、唐辛子などの現地の香辛料を使ったら、これが見事に当たったという。粟田氏は「郷に入れば郷に従えのことわざどおりで、現地の風味に合せた現地化が食の世界の成功の秘訣だ、と実感した」と語った。
清治氏はタイ1号店時からセントラルキッチン化めざした苦労を紹介
続いて、「8番らーめん」のブランドでラーメンはじめ、いくつかの和食展開を行うハチバンラーメンの清治氏が、この「食の現地化」問題について、現場体験を語った。
清治氏によると、ハチバンラーメンは東南アジアでタイに25年前に1号店を出した。その時に、現地パートナーとタイでは30店舗展開をめざしてビジネスを行うこと、30店舗はすべて味の同一化をめざすことを経営の基本にすることにし、とくに味の同一化のためにセントラルキッチン方式を採用し、つくったスープや食材をそれぞれの店に運んであとは現場で温めるようにした、という。
ところが第1号店出店当時、セントラルキッチンの工場でつくった食材を店に運ぶにあたって、バンコク市内の交通渋滞問題に遭遇し、現場の店の開店時間に間に合わないなどのトラブルを経験した。当時、冷蔵車もなかったため、品質保持のためにタクシーで早く運んだりするなど、現地化に際してさまざまな課題があった、と清治氏は語った。
清治氏によると、これら問題を克復しながら結果的に、現在ではタイに111店舗、香港で7店舗を展開する経営状態になった、という。その際、「チェーン展開にあたっては、味のみならず品質の保持などからもセントラルキッチン方式がベスト。そして現地パートナーとは、連携商品のラーメンの味を極めることなどで共通の問題意識を持っていることが大事だ。それをベースに、セントラルキッチンを機能させるためにはどうすればいいかなど、お互いにやれることを積み上げてパートナーシップを深化させていけば、必ずうまくいく」と現地化経営のポイントを語った。
「パートナーいかが」との呼びかけにミャンマー外食企業が呼応の一幕も
パネリストのネイ・リン氏や八馬氏も、これらの議論に参加して意見を述べたが、粟田氏がインドネシアでのうどんの成功事例をもとに、「ミャンマーでもきっとうまくいくはず。私は丸亀製麺ブランドの店をミャンマーで50店舗つくってみたい。どなたかパートナーの手をあげませんか」とシンポジウム会場に呼びかけたら、会場からミャンマーの企業関係者が呼応する一幕があった。
その企業関係者は「私自身は今、経営の第一線から引退した身だが、きょうのシンポジウムでの議論を聞いていて、ぜひ申し上げたい。ミャンマー人は麺類が大好きだ。日本のうどんはミャンマーで100%売れる。必ずパートナーの名乗り上げが出る」と述べて、会場を沸かせた。
また、そのミャンマー企業関係者は「昔は、ミャンマー料理以外は中国料理しかなかったが、正直言って、中国料理に飽きてきた。そんな中で、日本食の料理が登場したが、ミャンマーでは味がいい上に安全・安心で健康にもいいということで、ブームになっている」と述べた。
「食の現地化」が基本ながら日本オリジナル味との整合性どうする?の声
このあと、タイから参加したJROタイ支部長の浅井モスフードタイランド社長が日本食文化をアジアに定着させるにあたって、現地化がベースというのは当然のことながら、それぞれの企業の日本食の味や風味などのオリジナリティをどう維持すればいいのか、という問題提起を行った。
浅井氏によると、日本政府が2015年1月から中国向けと同様、タイ向けにもビザの発給条件を緩和したところ、円安・タイバーツ高も加わって富裕層などを中心に日本に旅行する人たちが増えた。その人たちが、日本で日本食文化を味わってみたら、タイで食べている味とは違う本物の味だ、といった評価が広がり、帰国して口コミで広がった、という。
さらに浅井氏は「現地の人たちの食や味の志向に積極対応する『食の現地化』の判断は間違っていないと考えるし、経営者としてもそれを基本にする考えに変わりはないが、一方で、日本に旅行して日本のオリジナル味を知って『本物の味だ』と本物志向を持った人たちを現場でどう取り扱うか、なかなか悩ましい問題だ。タイに限らずシンガポールやミャンマーでもあり得る話であり、それなりに対応を考えておく必要がある」と述べた。
清治氏、粟田氏、八馬氏はそろって味の現地判断に委ねる、との指摘
この点に関して、パネリストの清治氏は「ハチバンの場合、ラーメンなどの品質は日本も海外も同一がポリシーだが、味付けに関しては、海外のそれぞれの地域でローカル志向に合わせて対応するようにしている。タイの場合、現地の人たちの好みで砂糖をラーメンに入れるケースもある」と述べた。
また、粟田氏は「丸亀製麺韓国店の事例を申し上げよう。現地の韓国人パートナーが日本食好きの人で、『韓国でのうどんにキムチを入れてはダメだ。うどんのダシの繊細さが出ない』とキムチ入りうどんに批判的だった。当初、そのアドバイスを受け入れたが、1号店、2号店とも振るわずの結果だった。そこで、私は現地化策として、3号店からキムチ入りうどんに切り替えたら、これが大当たりだった。『食の現地化』は、それぞれの地域の風土や志向に合わせることが重要だ」と述べ、日本のオリジナル味とは別に現地化がポイントになるとの指摘だった。
ネイ・リン氏「日本からまだまだ学ぶこと多い、ぜひ互いに協力を」と発言
これらの発言に対して、八馬氏は「日本食レストランの現地対応の難しさを感じた。私たちは食品メーカーだが、味の素に関しては世界共通ながら、たとえばタイで売り出す缶コーヒーに関しては、タイの人たちの味のニーズに対応して甘味をかなり強くしている。アジアの現地での食品開発にあたっては、『食の現地化』に対応して、現地スタッフの判断を尊重するようにしている」と述べた。
ネイ・リン氏は最後に「今やヤンゴンで日本食レストランが100にものぼっている。ミャンマーの人たちの間で日本食が評価を得ているのは、味のよさ、品質のよさ、サービスのよさなどがあるからだろう。私たちミャンマーのレストラン関係者は、日本からまだまだ学ぶことが多い。ミャンマーはこれから発展する国なので、ぜひ互いに協力し合っていこう」と述べた。
シンポジウム後、日本食のメニュー提案・試食会でも意見交換
このシンポジウムのあと、会場の大ホール隣の会場で、日本食のメニュー提案、それに試食会が行われた。
パーク・ロイヤルホテル・ヤンゴンの日本料理長、本宮金雄氏が、スシを中心に数多くの日本食のメニュー提案を行ったもので、ミャンマーのレストラン関係者はじめいろいろなミャンマー関係者らが試食し、ここでも活発な意見交換が行われた。

ヤンゴン国際シンポジウム レポート
寄稿者:牧野 義司 氏(経済ジャーナリスト、メディアオフィス「時代刺激人」代表)







